福島県廣木酒造本店 「飛露喜」
以前にも“飛露喜”については、書かせてもらいました。所が、いい話を聞きましたので、皆さんにお伝えしたくて、今日の一言です。
栃木県大田原市の「たわら寿」さんのhpから転載させていただきました。http://www5d.biglobe.ne.jp/~tawara/index.html

そのころ廣木酒造本店をテレビ局が取材した。「将来、子供たちに『お父さんは昔、こんな仕事をしていたんだよ』と話すのもいいかな」。そう思って受けた取材だった。小さな蔵元を切り盛りする姿は、ドキュメンタリー番組として放送された。
番組を、東京都多摩市の小山喜八さんが見ていた。広く知られた地酒専門店「小山商店」の社長だ。小山さんから、電話で励まされた。「うまい酒を造れ」。試しに造った酒を送った。「この味では、首都圏では勝負出来ない」。厳しい言葉が返ってきた。
当時、日本酒の世界では「十四代」が新風を巻き起こしていた。山形県村山市の高木酒造が造る芳純な酒。評判を聞きつけ、初めて口にした健司さんは、奥行きのある味に圧倒された。「こんなうまい酒は、おれには造れない」。悔しさが、逆にバネになった。
酒米の五百万石を大吟醸なみに削った。酒米を水につける時間をタイマーできっちり計った。可能な限りの投資をし、蔵の設備を新しく変えた。「喜びの露が飛ぶ」。そんな思いが込められた酒は、口に含めば、うまさが小宇宙のように広がる味に仕上がった。
「端麗辛口」で一世を風靡(ふうび)した新潟県の酒とは、明らかに異なる独自の風味。
99年、こうして出来た「特別純米無ろ過生原酒・飛露喜」を小山さんに送った。小山さんからの返事は「100本もらおうか」。3日後、「またもらおうか」。相次ぐ注文にラベルを印刷に回す余裕はなく、母親の浩江さんが一枚一枚、「飛露喜」と筆で手書きした。
毎日書き続け、母親はけんしょう炎になった。
1999年突然現れた “飛露喜” は、瞬く間に地酒ファンの間で噂になる。
現在、「飛露喜」は引く手あまたで、蔵にも在庫はない。「一歩でも自分の酒造りの質を向上させたい」と、毎年夏には少しずつ蔵を改修。席を見据えた酒蔵造りにまい進している。一升瓶のラベルの文字は蔵元のお母さん、廣木浩江さんの手による。
「いい話でしょ」お酒の味に、一言の思いを伝えたくて書かせてもらいました。それでは、今日も「乾杯!」


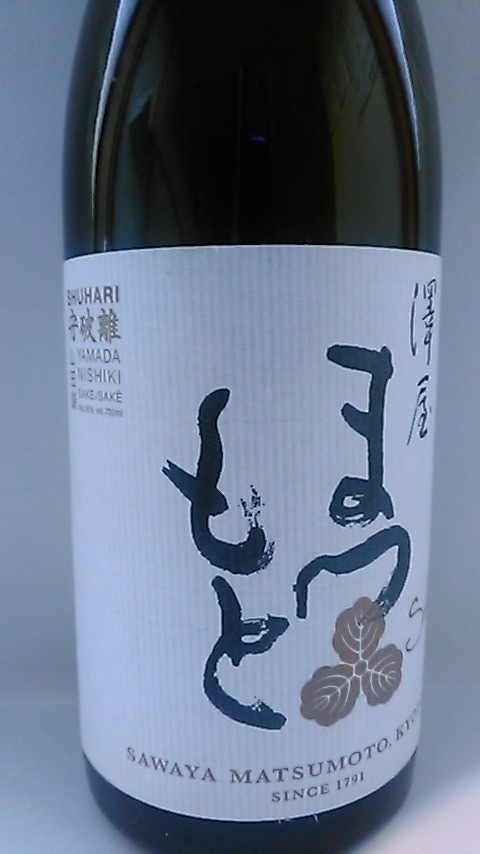






本当にいいお話ですね。
手をかければかけただけ、味にかえり、
評判が上がれば更に磨きをかけようと手をかける。
日本酒は、デリケートですね。深いですね。
そして、日々進化しているのですね。
今宵はひと口ひと口、更に大事に楽しんでみます。
今日も「ご返杯!」