草間 彌生美術館
ドーンと飛び込んだのはカボチャに水玉のオブジェ。見るからに迫力と草間彌生らしさが圧倒感をあたえる。
しかも屋上にただ一つ存在するその姿は、屋根の空間が吹き抜けになっているため青空と一体となって見る者は息を呑む。
美術館のフロアーは5階建、1階のエントランスから2~4階までギャラリーとして作品を見続けられる。世界平和と人間愛を語り続けた作品の数々だが、草間彌生自身は生と死を心の奥から見つめ続けていたようだ。
少女時代から繰り返し襲う幻覚や幻聴から逃れるために、幻覚や幻聴を描きとめる絵を描き始める。10歳頃からすでに水玉と網目模様をモチーフとしていたのが今でも生きている。
前衛芸術家と言われるが、その言葉だけで一括りには言えないほどの芸術感覚が感じ取れる。
1983年(昭和58年)には小説『クリストファー男娼窟』で第10回野性時代新人文学賞を受賞している。
ニューヨークで生きる男娼ヘンリーを通じて、鮮烈な〈魂〉の彷徨を描き出している。読み続けるほどに草間彌生の文章への才能も開花したものとして読み続けた。
そんな一冊の本も手に取って読むことができる。
東京メトロ東西線「早稲田」で降りれば徒歩7分ほど。弁天町の交差点を曲がればすぐに分かる。しかし木・金・土・日と祝日しか開いていない。しかも完全予約制で定員制でもあるのでチケットは事前予約で購入してもらいたい。
そして、帰りはそのまま神楽坂に向かい、どこかで一杯飲んでもらいたい。
やはり日本酒が神楽坂には良く似合う。








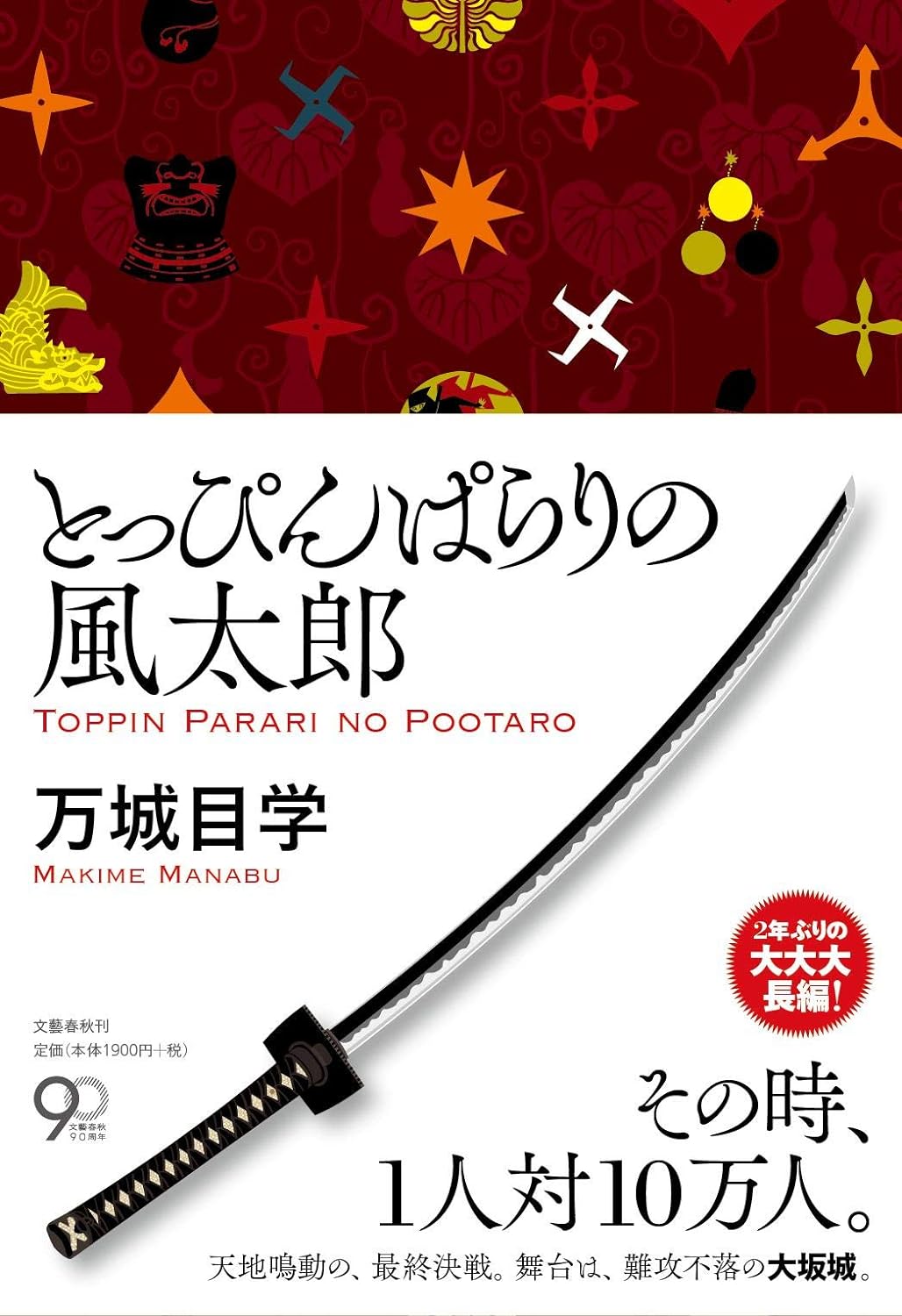

この記事へのコメントはこちら