直江兼続の時代

HNKの天地人、面白いですね。さて、そのテレビの画面の中で、お酒を飲んでいるシーンが出てきますが、あのお酒、濾過された澄んだ「清酒」ですよね。
ふと思うのです。あの時代にお酒は清酒として飲まれていたのか?という疑問が沸いてきました。
室町初期の『御酒之日記』(ごしゅのにっき)によると、化学知識などの学問がないこの時代に、今でいう麹と蒸米と水を2回に分けて加える段仕込みの方法、乳酸醗酵の応用、木炭の使用などが、明確に記されています。
この頃に現在の清酒造りの原型がほぼ整ったことになるのです、ですから安土・桃山時代には、つまり戦国時代には「清酒」として飲まれていたことになります。
そうなると、侍は清酒が手に入りますが、庶民はどうしていたのでしょうか。
そこが、分からないんですね。多分、私の想像では商人などの流通機構が整っている人たちは清酒が飲めたでしょうが、農村では「ドブロク」を飲んでたのではないでしょうか。
と想像で話しをしているのですが、江戸時代になると蕎麦食べながら、大工の熊さんなどが一杯やってるシーンがテレビなどで目にとまりますから、江戸時代などは庶民も清酒を飲んでいたと思います。
それでも、農家はどぶろく飲んでたんでしょうね。
ところで、今日の酒税法では、どぶろくについての規定がないそうです。密造に通じるので、製造は許されていません。例外として神事用に神社で少量の製造が許される場合があります。
現在市販されている「濁り酒」「白酒(しろき)(白貴)」などは、もろみを目の粗い袋で濾過したのち滓引(おりびき)せずに出荷するもので、酒税法上は清酒に属するのです。




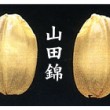

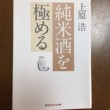
この記事へのコメントはこちら