トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代
その人は、いまだ僕の心の中で生きている。そしてギターを奏で、喉を震わせ歌い続けている。
でも僕は「悲しくてやりきれない」と思うのである。
そんな彼の映画が生まれた。トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代。
映画館に入れば、やはり同年代の観客が目に止まる。当たり前だと言えば返す言葉はないが、ザ・フォーク・クルセダーズからサディスティック・ミカ・バンドへと歩みを続けた時代の流れを知っている者も少ないのは当然である。その音楽性を高く、高く評価する人も年を取ってしまった。
かつての仲間たちが思い出を語る姿にフイルムは回り続ける。そしてその痕跡の合間に、懐かしき名曲が流されてくる。
「帰って来たヨッパライ」を共に、世に知らしめた北山修は語り続ける。その言葉はここでは語ることは辞めよう。是非映画館で知ってもらいたい。
加藤和彦の音楽性は僕のような年端も行かぬ子どもにも、その素晴らしさは驚きの連続であった。
ギターの奏でるメジャーセブン、そしてデミニッシュさらにマイナーセブンの流れに、心は奪われた。「何て美しいギターコードだろうか」その当時、こんな素晴らしいコードを奏でる人は僕の知っている限り誰もいなかった。そして12弦ギターを当たり前のように弾きこなす。その立ち姿は実に輝いて見えた。
そんな彼は音楽性以外に、ファッションでも食の世界でも一流を目指した。一流を求めるものは一流の作品を作れるものなのかもしれない。
その一流は最後に命を絶つ悲しき出来事で幕を閉じてしまう。
映画の最後には若いミュージシャンとかつての仲間が、「あの素晴らしい愛をもう一度」で共演をはたす。
流れる音に胸が潰れそうになった。苦しい思いで僕は彼に語った。
「死ぬなよ。死んじゃだめだろ」
そんな悲しみを癒す思いで、川崎で飲み、溝の口でもいつもの店で盃を重ね、登戸でやっと締めとなった。
思い出は金のかかるものである。


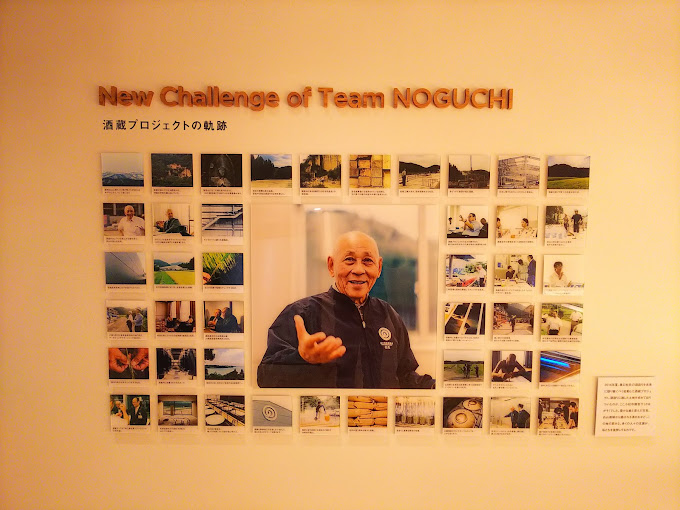







この記事へのコメントはこちら