19番の香り
渋谷のスクランブル交差点は、今日も人ごみの中で行きかう人の顔すら見ることができない。
今にも変わりそうな青信号の時、「あっ!」人の流れに押し戻されるようにあの香りがほんの少し鼻先をかすめた。シャネルの19番。
彼女は「5番は嫌い。19番が好きなの」そんな言葉を残して僕の前から姿を消した。
「彼女の香りだ」道行く人の逆方向を分け進みながら、彼女の香りを追いかけていた。「間違いない彼女に違いない…。」
渋谷のバグパイプという店で彼女と知り合った。今度二人で会おうよ、と約束した時「僕は同じ格好で待っているから」「私は白地に緑の葉柄が入ったワンピースで」と約束したのに、待ち合わせ場所に遅れてきた彼女は全く違う柄のワンピースで現れることになる。
「約束と違うじゃない」と語りかけても「当たり前でしょ。貴方の事信用してないもの。もしも一人で白地のワンピースで待っていたら絵にならないでしょ」言われるままに、僕たちの繋がりが始まったのだった。
彼女は日本酒の飲み方が実に美しかった。顎を少し上げて、お猪口を傾けながら最初の一口だけ小さな音でズズッとすすりながら酒を流し込む。どうして、と聞くと「お酒と空気を一緒に飲むと美味しくなるの」と言われたが、その頃の僕にはその味わいが理解できなかった。
一度彼女から叱責を受けたことがある。酒に酔って聞き覚えの日本酒蘊蓄を語った時、「そんな事はどうでもいいの。見てごらんなさい、この盃の中のお酒を。綺麗でしょ、その裏側に作り手の姿が浮かばない。だからお酒を飲んでも、酒に飲まれたら失礼でしょ」
そんな彼女は、笑うことがなかった。待ち合わせの場所でも、一緒に飲んでいるときも。ただ、僕が彼女に「ねえ、僕と一緒になってくれないかい」と伝えた時、初めて微笑みを見せてくれた。「馬鹿!」と言いながら後ろ姿を僕に向けた時、それが最後の時間になろうとは夢にも思わなかった。
それから何日もたたないうちに一通の封書が届いた。白地の便箋に緑の樹木がほんのり刷られた中には「ありがとう」の一言だけが書かれていた。
知っている限りの思い出から彼女の行先を追ったが、何も分からなかった。分からなかっただけでなく、彼女の年齢も、本名さえも僕は知らなかったのだ。
疲れ果てた僕に、唯一連絡がついた彼女の友人から知らされた言葉は、自らの手で命を絶ったことだった。そしてもう一つ、夫がいたことも。
僕は彼女の涙の色さえ知らなかった。真実がどれなのかさえ分からないまま、彼女の残り香として19番だけが心の片隅に残されていた。
渋谷の雑踏で居るはずのない彼女を追いもとめている。
僕は渡り切った交差点の隅で、街路灯にもたれながら大粒の涙を流していた。人目もはばからず、うずくまりながら肩を震わせ続けていた。







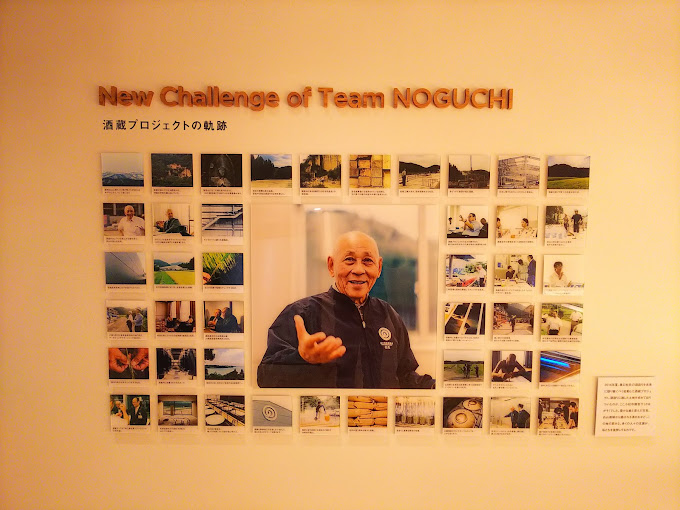


この記事へのコメントはこちら